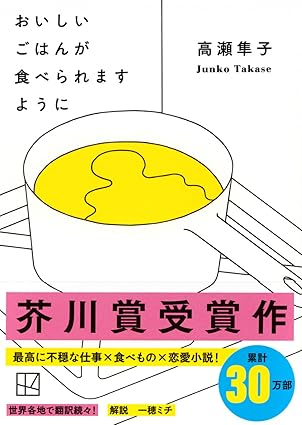
こんにちは。のーさんです。
2024年からはnoteを本格的に使用しています。
推し本紹介やコラムはあちらで更新していますので、良ければフォローをお願いいたします。こちらの記事は、noteが使えなくなった場合に備えた記録用です。
noteのアカウントはこちらです。
ののの@彩ふ文芸部(彩ふ読書会)
https://note.com/iro_doku
2025年8月9日、東京会場の課題本でした。
今回ぎりぎりまで読むかどうか迷いました。なぜなら、8月17日までに『罪と罰』を読み終えるという過酷ミッションに挑戦中だからです。
あ、嘘偽りがございました。過酷ミッションではありません。『罪と罰』企画は去年の12月頃にスタートしたので、読む期間は十分にありました。切羽詰まった状況に陥っているのは、私の得意技「先のばし十四回転」と「現実逃避スクランブル」と「ヒリヒリ感へのあくなき欲求9(よっきゅっきゅっ)」がフルコンボで決まったからです!
https://note.com/embed/notes/n9073613cfa2d
えーどーしよーーー。
もう日にちないけど150ページ追加しちゃうううう???『罪と罰』まだ800ページくらいあるんですけどもーーー。大食いの人が味変するみたいな感覚で読んじゃうううう???今読まなかったら読むのだいぶ先になりそうだしなーーー。
とりあえず、パラパラと冒頭だけ読んでみます。う、お、めっちゃドロドロしてるやん。おもろ。『罪と罰』は文字が小さいので全然ページが進まないのですが、こちらはさくさく進みます。これぞ、これぞ本来の私の読書ペースやー!!味変ならぬ読変ってやつでしょうか。そういえば自分が併読タイプだったことも思い出しました。
というわけで読むことにしました。100ページ読んで、あとは当日の午前中に読み終わるよう調整しました。
迎えた読書会当日。
私のテーブルは5名で読書会を行いました。登場人物それぞれの掘り下げや物語の構成について、自分の職場の話などなど、話題が広がって面白かったです。先月の『風の歌を聴け』を諦めたのもあって、より楽しい時間を過ごせました。
さて、課題本読書会も終えたので、ここからは私の感じたことを書いていきます。内容に触れるので「ネタバレあり」としておきますね。ご注意を!!
ここからネタバレあり
『おいしいごはんが食べられますように』は、二人の視点で物語が進みます。押尾と二谷です。たまに「今どっちの視点だっけ?」となることもあったのですが、芥川賞の選評読んでて気づきました。二谷は三人称、押尾は一人称で書かれていたようです。読み返してみたら確かにそうでした!気づいてなかった!
なんで視点の混乱があったのかというと、二谷パートでも押尾パートでも「二谷は」と出てくるからだったのかなと思いました。それで二谷パートかと思って読んでいたら「わたしは」と出てきて「ああ、今は押尾パートか」となるみたいな。ちゃんと読んでれば分かってたっぽいです。……自分で書いといてなんですが「ちゃんと」って何だ?
ワタクシ、本を読む前にはなるべく事前情報を入れたくないタイプ(裏表紙のあらすじも読まない)でして、作品によってはこういうことが起きるんですよね。
余談ですが『罪と罰』に関してはボリューム満点なので、こちらのマガジンで情報を仕入れてからパート毎に区切って読んでます。余談でした。
二谷も押尾も、それぞれの視点で芦川さんを追っています。読書会で話題になったのですが、二つの軸で物語が展開されていると聞いて、なるほどなー!と思いました。二谷は「食」、押尾は「人間関係」を軸に、芦川さんを見ていると。二谷と押尾が最後までやらずに途中でやめたのは、ここには明確な線引きがあるのだという表明でもあるのかななんて思いました。
二谷と押尾二人の注目の的である芦川さんの心理描写はありません。そのため、芦川さんが実際にはどんなことを考えていて、何故こんな振る舞いをしているのかは、読者が想像するしかありません。想像の余地があるところに、私は今回芥川賞受賞作らしさ的なものを感じました。芥川賞受賞作やノミネート作品を全制覇しているわけではないのであれですが、近いなと感じたのは今村夏子さんの『むらさきのスカートの女』です。
『むらさきのスカートの女』は、〈わたし〉の一人称で物語が進むのですが、〈わたし〉が注目しているのが「むらさきのスカートの女」です。読者はむらさきのスカートの女がおかしいと思って読み進めていくのですが、途中から「あれ?」となっていく構成になってます。こちらも終始〈わたし〉視点で物語が進むので、むらさきのスカートの女が何を考えているのかは分かりません。
『おいしいごはんが食べられますように』では、二谷や押尾の視点で芦川さんのことが描かれていますが、肝心要の芦川さんが何を考えているのかは分かりません。
読んでいたら村田沙耶香さんの『コンビニ人間』も浮かんできました。こちらは芦川さん的立ち位置にある古倉さんの視点で描かれていまして、古倉さん的には「普通」のことが、周囲にはおかしく映っている、みたいな描き方がされています。古倉さんと芦川さんは別著者の別作品の別人物ですが、もしも『コンビニ人間』のようだとしたら、芦川さんのあの振る舞いは芦川さんにとっては「普通」なのかもしれませんね。そんなことを思いました。
朝井リョウさんの『桐島、部活やめるってよ』も読んでて浮かんできた作品です。こちらは微妙に違いますが。タイトルにも出ている桐島が物語では一切出てこないっていう点で、「主役的立ち位置の人が何考えてるか分からない」ところが少し似ているなと思いました。ここらへんはすばる文学賞だからですかね?パクリとか悪い意味とかそういったわけではなく、そのあたりの雰囲気と似ているなーと感じた次第です。『おいしいごはんが食べられますように』が面白いと思った方は上に書いた作品も楽しめると思いますよ(ということが言いたかった)
たとえば作品中に芦川さんのパートがあって心理描写が書かれていたら、芦川さんは「芦川さん」という一人の人間(個体)になってしまったのではないかなと思います。ある種の象徴的存在から一つの個体になってしまうというか。答えを見てしまうというか。心理描写がないからこそ、芦川さんに対して読者は想像を膨らませたり、自分自身の勤める職場の誰それさんに当てはめたりなんかしちゃうことが出来ますが、「芦川さん」になってしまうと当てはめることは出来ません。著者の高瀬隼子さんが意図的にやっているのかどうか分かりませんが、私としては心理描写がなくて良かったなと思いました。仮に芦川さんの心理描写があって、物語が起承転結カチッとなっていたら、芥川賞というよりかは直木賞なのかなと思ったり。なんせ「いやーこりゃあ芥川賞受賞するわー芥川賞やわー」と思いながら読んでいました。
「食」と「人間関係」の話に戻ります。
「食」に関しては、現代社会は情報過多なので、一日三食に対してリソースを割きたくない(というニュアンスだったはず)という意見があり、分かるーってなりました。何を食べるか、食材は家にあるか、なければ買いに行くか、食べるものを変えて今冷蔵庫にあるもので済ませるか、作る時間。一食だけでも沢山の選択肢と時間が割かれます。コンビニ等で買ってしまえば楽です。
職場の「人間関係」に関しても「分かるー」と思いながら読んでいました。
ここ最近特に思うんですが……フルで働ける時期って短くないですか???
朝起きて出勤して終電近くまで働く。自分の全てを仕事に捧げることの出来る時期って、定年までの期間を考えたらそんなにない気がします。大卒でどこどこに就職したとして、しばらくはそんな働き方もやろうと思えば出来るでしょう。ただ、定年までの長い期間、どこかで働けない時期が出てきます。
自分自身に当てはめてみると、がむしゃらに働いていた時期の自分は押尾と似ています。今は物理的に働けない(保育園の迎えがあって残業できない日がある)ので、芦川さんの状況に関しても分かる気がしました。心理描写がないので何とも言えませんが。うちの職場には、仕事に人生を捧げているんかってなくらいに夜遅くまで働いて土日も顔を出している人がいるのですが、残業できなかったり私の都合で会議の日程をずらしてもらうことがあるとチクッとしたことを言ってきたりします。「だってしょうがないじゃないか」とえなりかずきばりに口を尖らせてちょい怒ぷんぷん侍化したり笑い飛ばしますが、私もかつてはそちら側の人間だったわけで、ちょっと羨ましくもあります。押尾側も芦川さん側も分かってしまう、かつ今は芦川さん寄りなので身につまされる感じがありました。
完全に感情移入できる人物はいませんでしたが、ポイントポイントで「あ、あの時期の私やわー」とか「ここあの人に似てるなー」なんて思い浮かべながら読んでいました。
猫のくだりに関しては、押尾はやりすぎ感もありましたが、そのエピソードの前のパートを読んでいると、「こういう心理状態になるの分かるわー」と思ったりします。押尾は押尾で視野が狭くなっていますけれども、他人の力を借りずに自分で何とかしたいなって思っちゃうんですよね。分かるう。
芦川さんみたいな人は、必ずといっていいほど職場の中にいます。仕事の出来る、基準値みたいなのがあったとして、その基準値を下回っているのが芦川さんです。私は気にしないようにしてはいますが、そこで厄介なのが現実世界にはもう一つの軸があること。「給料」です。「あの人、私より働いてないのに私より給料もらってんのかー」なんて考えがよぎってしまうことはよくあります。
押尾も二谷も職場からはいなくなって、芦川さんだけは残るというところはゾワッとしました。
あ、あと食に関しても人間関係に関しても「食べることが当然」「守ることが当然」みたいな「普通」があって、その普通に違和感を持っているのが二谷と押尾なのかなと思ったり。
だらだらと感想を書いてみましたが、身近なテーマを扱っているからか、今回は「分かるー」「あるある」みたいな感想が多かったですかね。この人のこういうところが理解できない、というよりかは、この人のここ分かるわーが多かった気がします。ペットボトルに口をつけるのはウェッとなりましたけれども。
こうして記事書くくらい読書会も楽しかったです。
以上です!!
長々とお付き合いいただき、ありがとうございました!!
