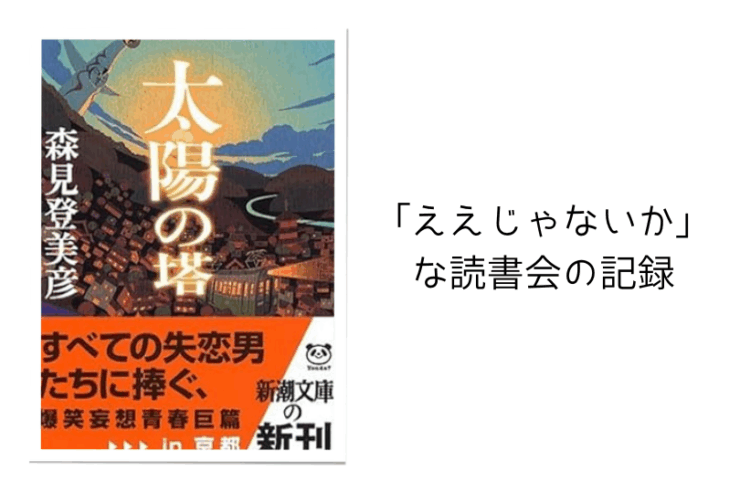
こんにちは。のーさんです。
2024年からはnoteを本格的に使用しています。
推し本紹介やコラムはあちらで更新していますので、良ければフォローをお願いいたします。こちらの記事は、noteが使えなくなった場合に備えた記録用です。
noteのアカウントはこちらです。
ののの@彩ふ文芸部(彩ふ読書会)
https://note.com/iro_doku
2024年12月21日、京都で読書会を開催した。通常版のレポートはこちら。
《京都》2024年12月21日(土) 『太陽の塔』課題本読書会レポート
あちらは「読書会に興味があるけどまだ参加したことのない方や初心者向け」に書いているので、真面目に書いている。対象の方はあちらをチェックしていただきたい。
二つに分けたのは、あちらには書けないようなことをこちらに書こうと思ったからである。開催レポートの延長戦。年内最後の読書会だったし、ええじゃないかええじゃないか!
以下、ネタバレを含むので各々で注意されたし。おそらく『太陽の塔』を読んでいなければ何のこっちゃな話であるし得られるものは何もない。もっとも、『太陽の塔』を読んだあとに以下の文章を読んだところで得られるものは何もない。諸君よ、教訓を求めるな。淡い期待を抱くことなかれ。
お食事中、通勤中の方は閲覧注意。
では、まいろう。
読書をするタイミングは人それぞれだと思うが、私はまとまった時間に読むことは少なく、通勤中やちょっとした隙間時間にパラパラと1、2ページだけ読むような「ちょい読み」を基本としている。食事中にも本を読むのだが、今回はタイミングが悪すぎた。麺類をすすっている最中に遠藤との嫌がらせ対決のシーンにぶち当たったのだ。オイオイまじか!うげえ!っとなり、私の目の前にある麺とスープの上に、脳内に浮かんだ虚構のアレがびっしりと詰まった状態でARの如く漂った。幸いだったのは、麺類がギトギトのものではなく、うどんだったことである。不幸中の幸いとはこのことかと私は身を持って言葉の意味を理解し一つ賢くなった。虚構のアレが漂いつつもしっかりとうどんを完食できたことは賞賛に値するだろう。味は分からなくなったが。しかしやはり著者や出版社には苦言を呈せねばなるまい。私のように食事中に読書する人間は少数派ながら存在するのだ。「食事中に太陽の塔を読んではならない」と注意書きの一つくらいあっても良かったのではないか。あったところでやるのだが。そんなバッドタイミングはあったものの、作品は非常に面白く愉快なものだった。これまでいくつかの作品を読んできたが、今のところ一番好きな作品である。ただ、これを一番好きといってしまうということは、私の価値観や下ネタレベルがその時代で止まってしまっていると公言しているのに等しく、それは読書会を主催する身としてはあるまじき事態であろう。読書会の中では一番好き「かもしれない」と付け加えておいた。
主人公の思考につっこみながら読み進めていったのでだいぶ時間はかかったのだが、その分一行一行じっくり味わいながら楽しめた。メモを取りながらだと読書会に間に合わなさそうだったので取らなかったのだが、印象的な文章はいくつもあった。読み終わったのは当日朝の10時頃だった。
さて、課題本読書会当日。
参加者は7名。男性ばかりかと思いきや、女性も3名参加予定だった。もう少し多ければ2グループに分けるのだが、人数的には1グループでの実施なのは決定である。それはそれとして、席の配置をどうするか。テーブルが1人用の勉強机みたいな形なので、他の会場とは違って配置が自由に出来る。前回の『夜は短し歩けよ乙女』では真四角にテーブルを配置したのだが、若干物理的な距離かあった。会議っぽくなってしまうのは嫌だなあと思いつつ自分では名案が浮かばなかったので、第1部が終わったあとに残っていたメンバーに投げかけた。今回は第1部から参加の方が4名おられたのだ。
いっそテーブルをなくしてしまってはどうか!
という提案を聞き、私はボソッと呟いた。
ええじゃないか。
すぐさま机たちがガラガラと音を立て部屋の端に追いやられた。残るは7つの椅子だけとなった。7つの椅子で円になる。距離はかなり近い!何やら男汁めいている気もする。素敵だ。しかし何かが、何かが足りない。なんだ。何が足りないんだ?!
「じゃあ、のーさんの前にだけテーブル残しときましょうか」
という提案を聞き、私はボソッと呟いた。
ええじゃないか。
ガラガラと音を立て部屋の端から机が戻ってきた。その席に座る自分を想像する。一人だけ偉そうな図が浮かんだ。……いや、良くない!読書会はフラットな関係のもと行われるのが望ましい。主催や進行がふんぞり返ってしまっては、意見が出しにくくなるかもしれない。私は平身低頭で机をそっと中央に置いた。中央に一つの机があり、その周りを7つの椅子が囲む形となった。その瞬間、そこにいた5名の見解は一致した。
こ、これは。
太陽の塔だ。
足りない何かが判明した瞬間である。
ええじゃないか!!
そんなやりとりをしていると(ええじゃないか)第2部から参加のお二人が来られ、7人全員が揃った。ちなみにこのとき来られたお二人のうち一人は初参加の方だったのだが、何となく見覚えのある方であった。「どこかでお会いしましたよね?」とナンパしそうになる声帯(ええじゃないか)をきゅっと締め、初参加の方に対していつも行っているように対応をし、席に促した。
HPの方の開催レポートにも書いたが(ええじゃないか)読書会の中で印象的だったのは「なぜ太陽の塔なのか」「水尾さんの人物像を描けない」「結末の捉え方」だった。なぜ太陽の塔なのかは明確な答えが出てきたわけではなかった気がするが、岡本太郎の話題にもなり(ええじゃないか)自分にはなかった視点から新たに考える機会を得れた気がした。水尾さんの人物像については皆で話していくうちに「私」との対比でじわじわと人物像が浮かび上がっていき、それが正解かどうかはさておき実に面白い!という結果となった。結末については、私と水尾さん(ええじゃないか)とは付き合えないんだろうな~と思っていたのだが、様々な意見が出て面白かった。
他にも印象的な話題は沢山あった。
この作品は男性目線で書かれている。もう20年前の作品なので今とはまた考え方や価値観などが変わっているのだが、「男同士なら感覚で分かるようなこと」が描かれている。(ええじゃないか)と書いててふと思ったが、異世界転生もののアニメをよく見たりするのだが、いくつかの作品においてはまだ結構20年前のノリ(ええじゃないか)と同じ描かれ方をされていたりする。時代は変わったと思ってはいても、変わらない点もあるのかもしれない。余談だが。それはさておき、男性目線で書かれていて、「男同士なら感覚(ええじゃないか)で分かるようなこと」が描かれているのだが、それはつまり女性にとっては感覚では分からないということである。今回の課題本読書会においては(ええじゃないか)女性が3名参加してくれていたこともあり、男女の違いにも話題が及んだ。読書会ではまず一人一人感想を述べたあとにフリートークに移るというスタイルで今はやっているのだが、それぞれの感想が無難に終わりフリートークに(ええじゃないか)移ったところで女性参加者から一石が投じられた。
「男汁とは?」といった一石である。
一石と聞くと小石を想像する方もおられるかもしれないが、これは巨石である。男性陣がうろたえた(ええじゃないか)のは言うまでもない。感覚で分かるようなことを言葉にするのは非常に難解なのだ。しかし、言葉にするのもたとえを出すのも非常に(ええじゃないか)厄介なパワーワードを、懇切丁寧に説明しようと試みる男もいた。下を俯きやり過ごそうとする男もいた。早く話題を切り(ええじゃないか)替えようと焦る男もいた。しかしこの一石を皮切りに男女の違いについての話題にも及ぶことが出来、日常会話では決して話題に出せないことを(ええじゃないか)話題にできたことは間違いないだろう。フリートーク中はなかなか会話が途切れることがなく、普段ならば10分か5分前にアナウンス(ええじゃないか)するのだが、アナウンスする間もなく読書会の終了時間となってしまった。一旦お知らせを挟んだが、その後もフリートークタイムは(ええじゃないか)賑やかなものだった。まず間違いなく年内最後の読書会にふさわしい会であったといえる。
会場の片付けをし(ええじゃないか)終わったあと、第2部から初参加だった方から声をかけられた。実は私は彩ふ読書会を(ええじゃないか)立ち上げる前にお世話になっていた(ええじゃないか)読書会でお会いしていた方だと発覚した。7、8年以上ぶりの再会(ええじゃないか)となるわけだが、お互いに何となく顔を覚えていたのである。「〇〇さんですよね?」(ええじゃないか)「やっぱり、そうですよね!」と盛り上がり、同時(ええじゃないか)に嬉しさがこみあげてきた。7、8年(ええじゃないか)以上ぶりに再会しても覚えていたこと(ええじゃないか)が何より嬉しかったし、読書会でお会いした人というの(ええじゃないか)はそれだけ印象に残るということが証明された瞬間でも(ええじゃないか)あったのだ。彩ふ読書会を立ち上げて(ええじゃないか)からはこちらの運営に四苦八苦して顔を出すことは出来ていないのだが、今も顔と(ええじゃないか)名前を覚えている人は沢山いる。また会いたいなあ、あち(ええじゃないか)らの読書会にも参加したいなあと思ったのであった。
ええじゃないかええじゃないか!!
というわけで、非常に良い形で年内最後の読書会を終えることが出来た。午前中には「ことのは読書会」の話も進めることが出来、来年もまた更なる楽しいことが出来そうな予感がしている。これから何が起こるのか、何がどうなっていくのかはまだ分からないが、予測できないことを楽しんでいけたらなと思っている。
そんなところで今日はおわる。
おわり。
