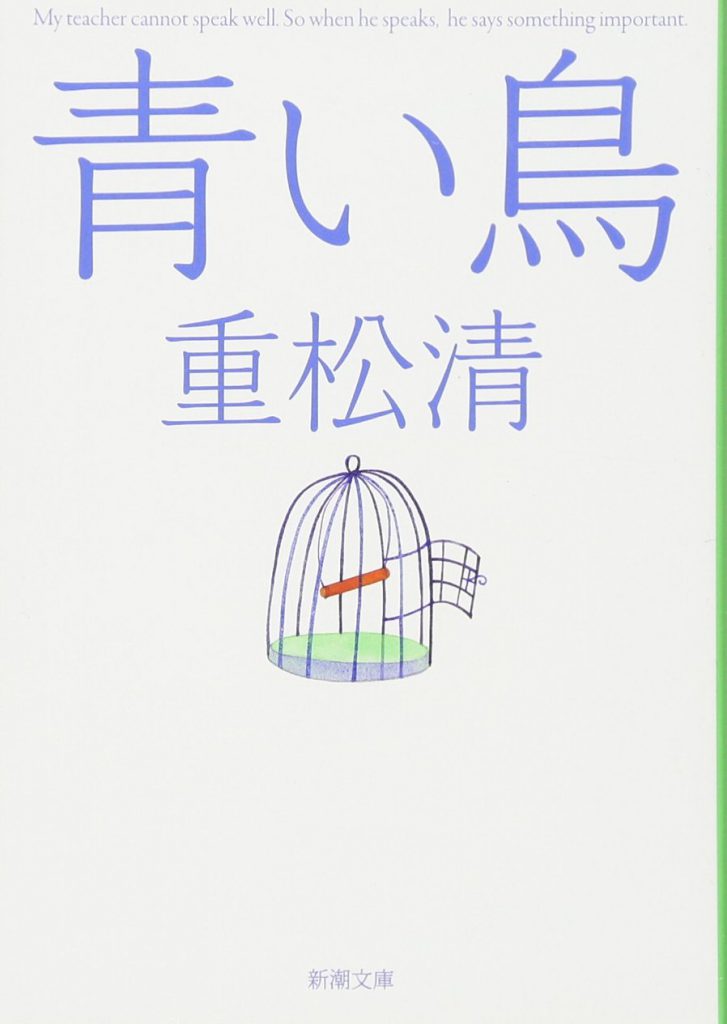
青い鳥
重松清
新潮文庫
多分、この本を自分で手に取る事はなかった気がする。取ったとしても、ずっと先になっていただろうし、その頃には他の作品に目移りして、結局読まずに人生を終えていたかもしれない。
4月京都読書会の課題本になったことで私は初めて重松清さんの作品に触れた。そして、感動した。途中何度も泣きそうになった。三月末に読んでいたらきっと泣いていただろう。そうならなかったのはひとえに私が春になって陽気な気分になっていたからである。再読する時には二月三月辺りに手にとって、思いっきり泣きながら読もうと思う。落ち込む時期でも、これを読めば浮上出来る。そんな秘密兵器を手に入れた気分。
重松清さんの名前は知っていたけれど、これまで作品を読む機会はなかった。
名前は知ってるけど作品未読な作家さんは沢山いる。まるで追い付かないのが現状だ。なるべく外れを選びたくないなどと保守的になってしまう私は、未読の作家さんの時は大抵何らかの大賞受賞作を最初に選ぶ。それが面白ければ二三作品読むこともあるけれど、同じ作家さんの作品を全て読破することはしていない。他の作家さんも気になるからだ。
「有名だから読まないといけない!」と、一種の強迫観念にかられて読書を始めると大体挫折する。せっかく読書するなら好きなものを読みたい。
そんな私の選書基準で行くと、重松清さんの青い鳥に手が伸びることはなかっただろう。タイトルで物語がイメージ出来ないと何となく億劫になってしまうのは悪い癖だ。
そんなわけで、課題本になったのは私にとってありがたい話だった。
もちろん、課題本になったからといって「読まなきゃ」って意識がなくなるわけではない。その意識は当然あったけど、自分にとって違うのは「知っているあの人が推薦した本」だということ。
一体彼はどんな風にこの作品を読み、そして課題本に選んだのだろう。そんな疑問も相まって、非常に楽しみに読書モードに入った。
読み進めていくうちに「もっと読みたい」となった。
青い鳥は短編形式になっている。全てがバラバラな作品というわけではない。共通して一人の教師が登場する。村内先生は上手く喋れない先生だ。吃音、どもる。けれど、たいせつなことは喋りにくくてもちゃんと言葉にする。必要な人のいつもそばにいてくれる。寄り添ってくれる。
こんな先生がいてくれたらな、と思う。
ヒーローらしいヒーローではないけれど、彼は間違いなくヒーローだ。
仕事柄、吃音の方とも実際お会いした事がある。最初の話に出てきた場面緘黙症の子とも関わりがある。そんな私でも、あ、こんな細かく描ける作家ってすげー!と思った。あとがきで重松清さんも吃音だと書かれていて、あ、なるほどなと腑に落ちた。
加害者の家族の視点、というのは目から鱗だった。なるべく人を傷つけるような言葉は発したくないと思っている自分でも、時には誰かを傷つけているんだろうな、という気がした。自覚もなく、鋭利な刃物で笑顔で容赦なくざくざくと。考えすぎると「何も言えねえ……」となってしまうけども、そういう視点は忘れないでおきたいなーと思う。
障害者、健常者という分け方には違和感を覚えるのだけど、そんな私でも障害者と関わっている時にふと「かわいそう」といった感情を抱くことがある。何故、彼らに対してそう思ってしまうのか。そんな感情を抱くこと自体が差別だと言われるかもしれないけれど、抱いてしまうこと自体は避けられないような気もする。
大人は表立ってそれを言う事はないから一見彼らにとって優しい世界が出来上がる。けれどそれは世界の違和感に気づきにくい構造を作り出してしまっているのではないか。私はその構造に訴えを起こしたい気もする。目に見えて分かりやすかったものが分かりにくくなっていて、何となくだけどハーモニーや一九八四年の世界を彷彿とさせる。子供は正直で、結構ズバズバと本人に直接言ったりするけれど、変に気を遣ったり遠ざけたりするよりもそちらの方が正常だという気もする。正しいとは何か?普通とは何か?
そんな風に色々と考えさせてくれる作品だった。こんな気分を味わせてくれる本。モヤモヤはモヤモヤのままだったりするけれど、考える機会にはなる。やっぱり読書って良いなあと思わせてくれる一冊だった。
