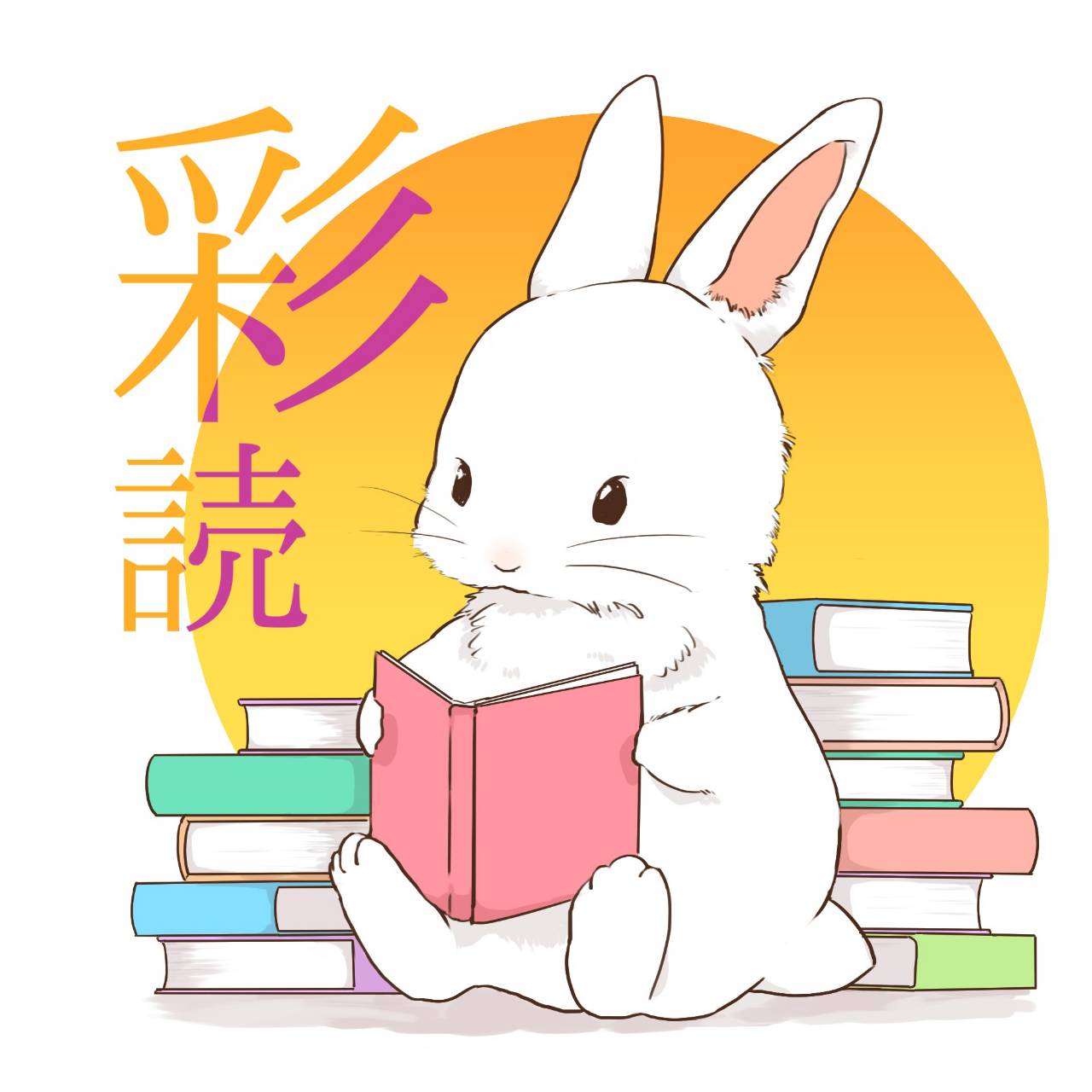こんにちは。のーさんです。
2024年からはnoteを本格的に使用しています。
推し本紹介やコラムはあちらで更新していますので、良ければフォローをお願いいたします。こちらの記事は、noteが使えなくなった場合に備えた記録用です。
noteのアカウントはこちらです。
ののの@彩ふ文芸部(彩ふ読書会)
https://note.com/iro_doku
先日、テレビで『限界!!ご褒美ガール』という番組がやってました。
本を読みながら何の気なしに観ていたんですが、次第に本を読む手が止まり、ソファに座りなおしてしっかりと視聴していました。何だか面白かったのと、「分かる!」という部分があったからです。
ご褒美ガールは「人生のいきがい=ご褒美」のために人生を捧げる女性たちに密着するドキュメントバラエティ番組だそうです。初めて観ました。
星野リゾート全制覇を目指す女性が密着取材されていて、その女性は宿泊に向けて美容院で前髪を切り、星野リゾートとギャップを出すためにビジネスホテルに前泊し、料理を楽しむために前日は断食までしていました。それらの儀式を終えての当日。女性の表情は違っていました。きらきら輝いていて、とてもウキウキした様子でした。
これ、分かる……!!と思っちゃったんですよねー。
私の場合も、課題本読書会をより楽しむために儀式やってんなあと。
課題本読書会とは、事前に指定された本を読んできて当日語り合う形式の読書会のことです。
読書会とはまず何ぞや?という方は、下記リンク先をご参照いただけたらと思います。
読書会とは、読書が好きな人におすすめな交流会です
皆さんは読書会って知ってますか?読書会とは、ざっくりいうと本が好きな方が集まっておしゃべりをする会です。読書をしない方はま
iro-doku.com
私は彩ふ読書会という団体の主催もしてまして、関西在住なんですが東京でも読書会を開催しています。「なんで東京でも?」という疑問にはこちらで片がつきました。
推し本披露会(おすすめの本を持ち寄り紹介しあう形式の読書会)も、課題本読書会も、主催する以前から参加していた時期を含めると十年近く参加していることになります。それだけ参加していて飽きないの?とお思いかもしれませんが、これが飽きないんですよねー。
読書会でご一緒する方も、読書会での話がどう転んでいくかも、回によって様々です。自分が着目してなかった部分に着目している方がおられたり、全く違う視点からの意見があったりして、読書会の流れが大きく変わることがあります。始まるまで、いや始まってから終わるまで予測不可能なので、そこが面白かったりします。
それだけで十分に楽しめるのですが、これはいわば他人軸での楽しみ方でもあります。こっちを主軸として読書会に挑むと、「今日は面白い発言がなかったな」とかみたいに、読書会や読書会参加者を評価してしまう方向に進んでしまい、楽しめない回が増えていくことでしょう。
自分軸で読書会にのぞむこと。そのために、読書会当日までの儀式を作ることと、その儀式を試行錯誤してみることかな〜、と十年近く経つと思います。
私の今の儀式はこちらです。
「読書会当日ぎりぎりに課題本を読み終わる」
これだけなんですが、ここに至るまでに長い年月がかかりました。この儀式にもデメリットがあるので、今後も試行錯誤は続くことでしょう。とりあえず、今はなぜこの儀式になっているかというと……。
早めに読み終わってしまうと、読書会当日に内容を忘れているから!!
一ヶ月前に読み終わっていたりすると、まあまあ忘れているんですよね。あらすじとか展開は覚えていても、登場人物たちの名前を忘れていたり、印象的だったシーンもどのページだったかなと忘れてしまっていたりします。で、結局読み直すことが何度かありました。
メモをしながら課題本に挑んでいた時期もありました。本を読んで印象的だったシーンや文章があればメモアプリを開いてその都度メモする方法です。この方法で読むと忘れ度は減るのですが、読むのに時間がかかってしまう事態となりました。印象的なところしかメモしてないので自分で前後の流れが分からず、「これ何のメモだったっけ」となることもよくありました。
そもそも寝たら大体のことは忘れてしまうタイプなんですよね。なんて課題本読書会に不向きなタイプなんだ……と思ってしまったりしますが、だからこそどういうタイミングで読めば読書会をより楽しめるか戦略を練ったりします。今回は自分の読み方があかんかったなーと思ったら、次はこういう風に読んで当日挑んでみよう、と考えるのが楽しいです。で、今のところ直前ぎりぎりに読むパターンでいけてます。
ただ、この儀式にもデメリットがありまして、ぎりぎりであればあるほど細部を覚えているのは良いんですが、ぎりぎり過ぎて読書会までに読み終わらない可能性との戦いが待っています。私自身はそのヒリヒリ感すらも楽しんでしまっているので最早楽しみ方が変態的領域に達してきている感は否めません。今のところ〆切効果もあり読み終わらなかったことはないんですが、ドーパミンはどばどばびっしゃあと放出しながら読み終えているので健康には害な気がしています。
あと、ぎりぎりに読み終わるということは「再読をしていない(一回しか読んでいない)」「他資料などには触れる時間がない」状態のまま読書会に挑んでいるということでもあります。詳しい人がいたら教えてもらおうというスタンスでいるので私自身は満足しちゃっているのですが、教養を深める目的で参加された方や、他人軸で楽しみに来られた方に対して提供出来るような深い知識は、残念ながら持ち合わせておりません。
主催たるもの、あるいは進行するからには、その作品に詳しくなければならない!と考えた時期もありました。著者の他の作品を読んだり、ネットの感想をチェックしたりもしてましたが、どれだけ詰め込んでも付け焼き刃ですし、自分以上に詳しい人はたくさんおられるんですよね。そこを突き詰めるよりかは、自分自身の感じたままの意見を伝えりゃ良いか〜というスタンスで今はやっています。
とまあこんなスタイルで昨日も京都で『手のひらの京』を課題本に読書会を行いました。とにもかくにも、私は言いたいことは言えましたし、京都出身の方からのご意見も聞けましたし大満足でした。他の方が楽しめたかどうかは……知らん!(暴言)
課題本読書会にフォーカスして書きましたが、推し本のほうも同じですね。おすすめしたい本をどう紹介するのか。当日までに試行錯誤すると、より読書会当日を楽しむことが出来るのではないかなと思っています。
読書会の楽しみ方は人それぞれ。
ご自身の楽しみ方を模索しながら、参加してみてはいかがでしょうか。
では、また!!